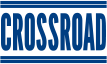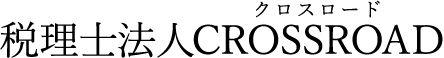経営理念について
会計・税務・経営コンサルティングのご相談は大阪市中央区と東京都港区の税理士法人CROSSROAD(クロスロード)
居住用の区分所有財産の評価について

今回は、令和6年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した「居住用の区分所有財産(いわゆる分譲マンション)」の評価方法についてご説明します。
1.居住用の区分所有財産とは
居住用の区分所有財産(一室の区分所有権等)とは、一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室に係る区分所有権(=家屋部分)および敷地利用権(=土地部分)をいい、いわゆる分譲マンションのことになります。
居住の用に供する専有部分とは、一室の専有部分について、構造上居住の用に供することができるものをいいます。これは原則として、登記簿上の建物の種類に「居宅」を含むものが該当します。
2.居住用の区分所有財産の評価について
居住用区分所有財産の評価については、法令解釈通達により定められており、次の算式にて計算をします。
【算式】
|
建物部分の従来の相続税評価額 × 区分所有補正率 +敷地利用権部分の従来の相続税評価額 × 区分所有補正率 |
なお、居住用の区分所有財産が貸家および貸家建付地であるときの、その貸家および貸家建付地の評価並びに小規模宅地等の特例の適用については、この通達の適用後の金額をもとに行うこととなります。
3.居住用の区分所有財産には該当しないもの
次に掲げるものについては、居住用の区分所有財産の評価の適用はありません。
・構造上、主として居住の用途に供することができるもの以外のもの(事業用のテナント物件など)
・区分建物の登記がされていないもの(一棟所有の賃貸マンションなど)
・地階(登記簿上「地下」と記載されているものをいいます。)を除く総階数が2以下のもの(総階数2以下の低層の集合住宅など)
・一棟の区分所有建物に存する居住の用に供する専有部分一室の数が3以下であって、 その全てを区分所有者又はその親族の居住の用に供するもの(いわゆる二世帯住宅など)
・ たな卸商品等に該当するもの
※借地権付分譲マンションの敷地の用に供されている「貸宅地(底地)」の評価をする場合などにも、この居住用の区分所有財産の評価の適用はありません。
4.改正が行われた背景
令和5年度与党税制改正大綱において、次のように記載がされました。
|
(5)マンションの相続税評価について マンションについては、市場での売買価格と通達に基づく相続税評価額とが大きく乖離しているケースが見られる。現状を放置すれば、マンションの相続税評価額が個別に判断されることもあり、納税者の予見可能性を確保する必要もある。このため、相続税におけるマンションの評価方法については、相続税法の時価主義の下、市場価格との乖離の実態を踏まえ、適正化を検討する。 |
相続税法では、相続税法22条において、相続等により取得した財産の価額は、当該財産の取得のときにおける時価(=客観的な交換価値)によるものとされています。この評価方法は国税庁の通達によって定められているものになります。
このうち、マンションについては通達によって評価した「相続税評価額」と「市場売買価格(時価)」とが大きく乖離しているケースがありました。このような乖離があると、相続税の申告後に国税当局から、路線価等に基づく相続税評価額ではなく鑑定価格等による時価で評価をし直して課税処分をされるというケースも発生しています。また、この乖離を利用した、タワマン節税と呼ばれる相続税対策があります。
タワーマンションは高層階になるほど市場価格が高額になりますが、従来の相続税評価額は階層によって金額が高くなるものではなかったことから、大きな資産圧縮を図ることができていたと言えます。時価とは、客観的な交換価値のことをいうとされていますが、通達にそって評価することが原則とされており、それが著しく不適当である場合に限り、通達以外の方法で評価をすることになります。ただし、行き過ぎたタワマン節税などにより、課税処分を受ける可能性があることから、マンションの市場価格と相続税評価額の乖離は、予見可能性の観点からも評価方法の見直しにより是正することが適当であるという考えのもと、今回の改正が行われたものと思われます。
なお、この改正により、タワマン節税の効果が全くなくなったと言えるものではなく、従来と比べるとその恩恵は少なくなるかもしれませんが、引き続き検討してもよい対策の一つではあると思われます。
相続税対策については、税理士法人CROSSROADに、お気軽にご相談ください。