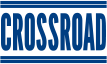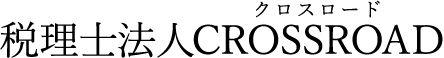外食産業向け業態転換等補助金、申請スタートです!
税務
令和4年6月15日、農林水産省は新型コロナウイルスの影響により経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う業態転換等の取組を支援する為、
『令和4年度 外食産業事業継続緊急支援事業のうち業態転換等支援事業』の公募を開始しました。